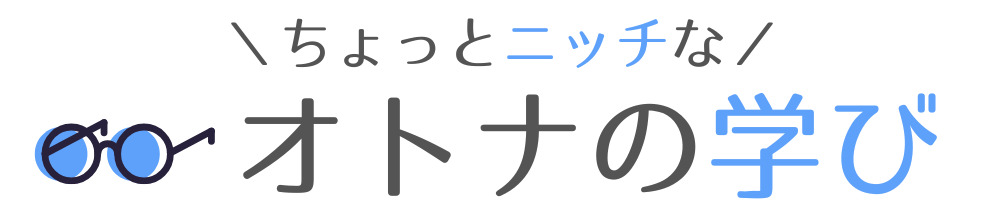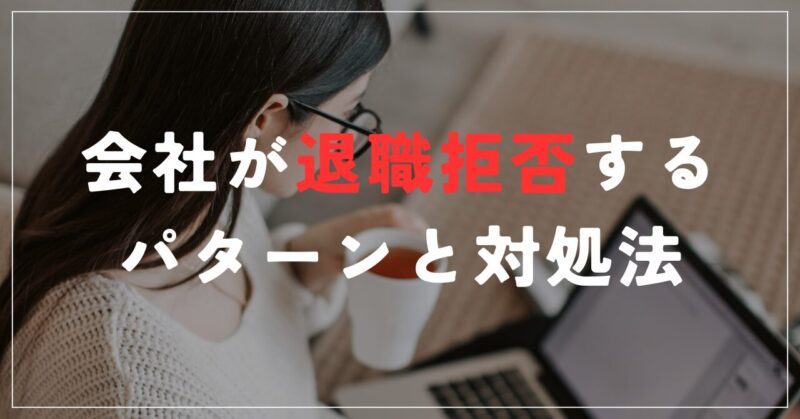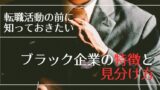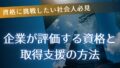本ページにはプロモーションが含まれています。
現在務めている会社を退職しようか検討中の方はこんな悩みはありませんか?
✔ 退職の申し出を拒否される
✔ 話し合いに応じてくれない
そこで本記事は、会社が退職を拒否する場合の対処法を紹介。記事を読むメリットは以下のとおりです。
〇 退職を拒否された際の対処法がわかる
〇 退職時に気を付けるポイントがわかる
具体的には、会社が退職申し出を拒否するパターンと対処法を紹介。人事として様々な退職トラブルに対応した経験をふまえた内容です。会社を辞められなくて困っている方はぜひ参考にしてみてください。
\エントリーシートの文章化をAIが補完/
会社が退職拒否するパターン

従業員が退職を申し出た際、会社が何らかの理由をつけて退職を拒否する(または先延ばしする)といったケースはよくあります。ここでは、会社側が取る退職を拒否する主なパターンと対処法を解説します。
上司が退職申し出を握りつぶす
会社が退職を拒否するパターン1つ目は「上司が退職の申し出を握りつぶす」です。
部下に辞められると仕事が回らなくなったり、自身の人事評価が下がったりと、真っ先に影響を受けるのは直属の上司。状況によって部下の退職申出を握りつぶす(または知らないふりをする)ことがあります。

上司に退職を申し出た際、以下の対応をされた時は注意しましょう。
・「俺に言われても困る」
・「忙しいから後にしてくれ」
・「そんなの聞いていない」
とりわけ繁忙期だったり、人手不足に陥っていたりするとこのような対応をされるケースがあります。上司がなかなか取り合ってくれない場合の対処法は以下のとおり。
・上司の上長へ相談する
・本社の管理部門(人事)に相談する
上司が中間管理職であれば上司の上長、その部門のトップなら本社の管理部門に相談するのがおすすめです。相談する際は、以下のように問い合わせてみましょう。
「○月○日付で○○さん(自分の上司)に退職願を提出しましたがご覧になりましたか」
上司が会社に報告していない場合、上長や管理部門が事実確認してくれます。

退職を申し出る際のポイントは、書面(退職願い)で提出すること。
口頭での意思表示は、上司に握りつぶされるリスクが高くなります。会社としても「退職の意思表示はなかった」と判断し、無断欠勤や懲戒事由に発展する可能性も否定できません。
そういった事態を避けるためにも、退職の意思表示は必ず書面で行い、上司へ提出する際はコピーを取っておきましょう。
労働契約や就業規則を楯にする
従業員が退職を申し出た際、会社側が労働契約や就業規則を理由に退職を拒否するパターンもあります。悪質な会社では、労働契約を締結する際、以下の定めを契約に盛り込むケースもあります。
・自己都合により契約期間の途中で退職する場合、一定の金銭を支払うこととする。

「今辞めるとペナルティ(金銭負担)が発生する」と脅すパターンです。
ついつい退職願いを取り下げそうになりますが、そこは毅然と対応しましょう。なぜなら上記の取り決めは「違約金・損害賠償の予定」にあたり、労働基準法第16条によって無効となるからです。
<労働基準法第16条>
・使用者は労働契約不履行につき違約金※を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
※労働者が契約上の義務を履行しない場合、損害発生の有無に関わらず支払義務を負う金銭のこと
労基法16条は、会社による過大な賠償額や違約金によって労働者の退職の自由が損なわれるを防ぐための法律。退職の申し出に際して金銭を要求する場合は、労基法16条を掲げて対処できます。ただし実際に損害が生じた場合、使用者が労働者への損害賠償請求は禁止されていません。

退職申出の時期によっては「就業規則違反」を主張するケースもあります。
就業規則には「退職申出の期限」が定められており、その期限を守らずに退職申し出をした際に起こるパターンです。ちなみに多くの企業は、就業規則に以下のような定めがあります。
・退職については、1か月前までに申し出なければならない。
その一方、労働者の退職する権利は民法627条で以下のように定められています。
<民法第627条>
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
法律上は2週間前の申し出によって退職が認められているため、1か月前までに申し出しなかったことを理由に退職を拒否することはできないことになります。

就業規則に法的拘束力はないので、法律が優先されるということです。
ただし後任の人選や業務引継ぎにあたり、早めの退職申出が望ましいのは事実。退職までに十分な期間を設けられない場合は、会社とよく話し合いましょう。円満に退職するためにも、業務に支障が出ないよう調整するのがおすすめです。
懲戒処分や損害賠償をほのめかす
従業員が退職を申し出た際、会社が懲戒処分をほのめかすことがあります。たとえば「プロジェクトに支障が出た」「職場の風紀を乱した」などと言いがかりをつけ、懲戒処分にかけるぞと脅すパターンです。

ちなみに会社が懲戒処分を行うには、就業規則に明確な規定がある場合のみ
就業規則に定めていても、合理的理由がなく社会通念上相当と認められない場合は懲戒処分は無効です。退職申出だけで懲戒事由に該当することはないので、毅然とした態度で対応しましょう。
育成費用や業務上の損失を上げて、損害賠償をほのめかして退職を拒否するパターンもあります。
<損害賠償をほのめかす例>
・お前を採用するのに、手間や費用がどれ程かかったと思っているんだ。
・教育研修に要したコストは○○○万で、△△△万の売上を上げないと損害が出る。
ですが、会社から労働者への損害賠償請求は、原則として「労働者に故意または重過失がある場合」に限られます。労働者への損害賠償請求を認める判例もありますが、会社と労働者は損害を公平に分担すべきとされており、労働者が一方的に損害を負担することはありません。
そもそも退職の申し出を理由に会社が損害賠償を請求するのは一種の恫喝であり、根拠に乏しいことがほとんどです。毅然とした態度で対応し、公的機関や弁護士に相談するようにしましょう。
\スキルゼロからフリーランスへ転身/
会社は退職申出を拒否できない
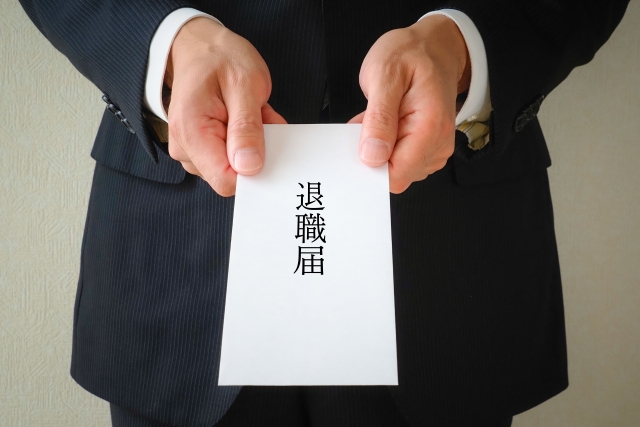
ここまで、会社が退職申出を拒否するパターンと対処法を紹介しました。

そもそも原則として、会社は労働者の退職申出を拒むことはできません。
民法第627条によって労働者は「退職の自由」が認められているからです。
<民法第627条>
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ちなみに民法627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」と条件が付されています。これは期間の定めのない雇用契約を締結する労働者(正社員)を想定したもの。
パートやアルバイトなど契約期間に定めがある労働者の場合は「やむを得ない事由」がある場合を除き、契約期間満了まで退職が制限されます。民法628条では以下のように定めています。
<民法第628条>
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

やむをえない事由の具体例は、以下のような理由で労働継続が困難になった場合です。
・ハラスメントで心身を病んでしまった
・怪我で仕事を続けられなくなった
・家族の介護のため、実家に戻った
なお、有期労働契約であっても、契約期間の初日から1年を経過すれば退職が認められています(労働基準法附則第137条)。無期雇用と同様に退職を認める企業もあるので、判断に悩む場合は就業規則を確認してみましょう。
退職と競業避止義務の関係

従業員が退職を申し出た際、企業から「退職後の競業避止義務の誓約書」の提出を求められる場合があります。これはライバル企業へ人材やノウハウの流出を防ぐための措置。
開発中の新技術の情報を保有したままライバル企業に転職することを禁止するなど、特別な状況下でのみ認められるものです。

よほどのことがない限り、転職活動に支障はありません。
競業避止義務は「職業選択の自由」という憲法上の権利を制限することになるため、簡単には認められないもの。競業避止義務を課すには、企業として「守るべき利益」がある場合に限られ、義務の範囲を最小限にすることが求められます。
\リゾートバイトで新しい自分と出会う/
退職拒否された時の対応

退職申し出を会社が拒否する場合、公的機関や弁護士を活用するのも一つの手。以下それぞれ解説します。
公的機関へ相談する
退職トラブルにおける公的機関の相談先は、労働局と労働基準監督署の2つ。勤務先の事業所所在地を管轄する労働局や監督署が窓口となります。

労働局ではワンストップで労働相談にのってくれるほか電話相談にも対応。
必要に応じて、企業に対して「助言・指導」や「あっせん」をする場合もあります。労働基準監督署に相談するのも手ですが、労基署はあくまで監督機関であり、企業への指導助言やあっせんは対応していません。
まずは都道府県労働局が設置する「総合労働相談コーナー」に問い合わせるのがおすすめです。
弁護士に相談する
退職申し出を拒否されたり、退職に関する交渉が見込まれたりする場合は、弁護士に相談するのも手です。

弁護士法72条の禁止行為(非弁行為)に該当する事案は、必ず弁護士を活用しましょう。
<弁護士法第72条>
弁護士(弁護士法人)でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件、その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
退職に関する具体的な事例として、以下のような内容が該当します。
・退職理由を巡って企業と揉めた際の交渉
・未払残業代や退職金などの支払い請求
・ハラスメントへの対応と慰謝料の請求
退職代行会社を活用する
会社との退職交渉を「退職代行会社」に任せる方も増加中。会社とやりとりをせずに済むため、精神的負担が少ないことが支持される理由です。
本人がメンタル不調に陥っていたり、会社と対立状態にあったりと、会社に行くのが難しい場合におすすめします。

注意点は、一般法人の退職代行業者は会社との交渉ができないこと。
退職届を代理で提出するだけなので、離職票の交付や私物返還の際にトラブルになる可能性があります。そのため、代行会社を選ぶ際は「労働組合が運営する退職代行」がおすすめ。

労働組合の退職代行であれば、会社との交渉ごとに対応できるからです。
労働者は憲法第28条で団結権・団体交渉権・団体行動権(以下、労働三権)が保障されています。労働三権を保障するために労働組合法があり、それに基づいて労働三権を保証する団体が「労働組合」です。
<労働組合>
労働者が団結し、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体
会社と退職に関する交渉ができるのはもちろん、未払残業代など賃金に関する交渉も可能。一般の退職代行会社では対応できないため、労働組合の退職代行に依頼する大きなメリットです。
ほかにも会社が不当に賃金や退職金を支払わない場合、会社との賃金交渉を通じて賃金や退職金を受け取れる可能性が高まります。交渉が成立して賃金を受け取れれば、その一部を代行費用に充てるなど、退職者本人の費用負担も軽減できます。
\無料・無制限でプロにキャリア相談できる/
退職時の注意点

最後に、いざ退職するとなった時の注意点を解説します。細かな部分もありますが、会社と揉めることがないよう気を抜かずに対応しましょう。
退職届などの書類提出
退職届をはじめ、退職に関する手続き書類は会社へ遅滞なく提出しましょう。

退職日が後ろ倒しになるなど、デメリットを被る可能性があるからです。
退職届の書式は、任意もしくは就業規則に定められた書式を使用します。退職の申し出と同時か、遅滞なく提出するのが一般的。競業避止義務の誓約書など、疑問のある書類は提出を拒んでも差し支えありません。
年次有給休暇の消化
年次有給休暇が残っている場合は、退職日(予定日)までに使い切りましょう。

会社に遠慮して、年休消化をしぶる必要はありません。
余った年休を退職後に使うことはできませんし、年休の買い取りは企業の義務ではないからです。年休を残しても労働者が損するだけなので、必ず使い切るようにしましょう。
私物の回収は忘れずに
年次有給休暇の消化予定をふまえて、最終出勤日までに私物はすべて回収しておきましょう。私物を残して退職してしまった場合、残った私物を着払いで複数回にわたり自宅へ送付するなど嫌がらせをされるケースもあります。無用なトラブルを避ける上でも、私物はすべて持ち帰りましょう。
身元保証人へ連絡しておく
会社に退職の申し出をしたら、念のため身元保証人にもその旨を連絡しておきましょう。会社と退職で揉めている場合、身元保証人にクレームや損害賠償を請求してくる可能性があるからです。身元保証人が困惑しないよう、あらかじめ状況を伝えておくことをおすすめします。
会社の情報は持ち出さない
退職する際は、顧客情報や商品情報、その他の機密情報を持ち出してはいけません。些細な情報であっても、不正競争防止法違反などを理由に刑事告発されるリスクがあるからです。
退職後にSNSなどを通じて会社を批判する行為も、偽計業務妨害などの問題になる可能性があるので絶対にやめましょう。
\相性で診断!20代向け転職支援サービス/
まとめ
以上、会社が退職を拒否するパターンと対処法を解説しました。

退職で会社と揉めるのは一種の紛争。
長引くと、本来受け取るべき賃金や退職金が支払われないなどのリスクもあります。毅然と対応しつつ、話し合いが難しければ、公的機関や弁護士、退職代行の活用をおすすめします。
別記事で、ブラック企業の特徴について解説しています。気になる方はこちらもどうぞ。