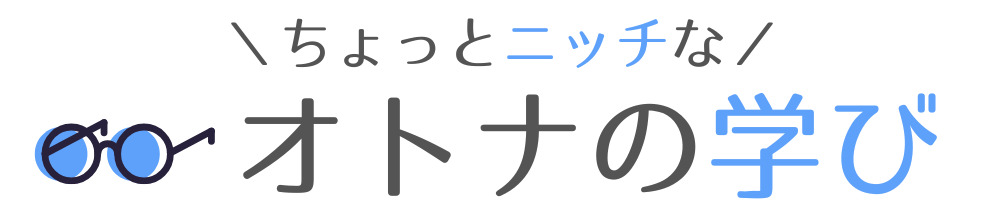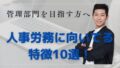本ページにはプロモーションが含まれています。
管理部門で労務担当として働く方はこんな悩みはありませんか?
✔ 業務で行き詰まるようになった
✔ 労務担当として知識不足を感じる
そこで本記事では労務担当に必要な知識を紹介。記事を読むメリットは以下のとおりです。
〇 行き詰まり解消のヒントが得られる
〇 労務に求められる基礎知識が分かる
以下、労務の役割と仕事内容をふまえて、労務担当に必要な基礎知識7選を解説します。筆者の10年以上に及ぶ実務経験に基づく内容なので、ぜひ参考にしてみてください。
\労務関連資格を豊富に扱うオンライン予備校/
労務担当に必要な基礎知識
以下、組織での役割や仕事内容をふまえて、労務担当に必要な基礎知識7選を解説します。
規則規定類の知識

労務担当に必要な基礎知識1つ目は、規則規定類の知識です。労務担当に規則や規定の知識が必要な理由は以下のとおり。
✔ 就業規則や労使協定を管理するため
✔ 法改正等に伴う変更に対応するため
✔ 労働組合や従業員等へ説明するため
労務担当は就業規則をはじめ、労使協定や内規など、企業の規則・規定類の管理を担っています。
・就業規則
・労使協定
・各種内規…etc.
たとえば就業規則には、就業に関する基本的なルールがまとめられています。社内の勤怠管理を取りまとめる労務にとっては必須の知識。

問合せや相談に対応するためにも、内容を熟知しておく必要があります。
労使協定に関しても、36協定や変形労働協定など労働時間管理に欠かせない内容がいくつも含まれるため、協定の種類や締結内容を把握しておかねばなりません。職務権限規程や文書管理規程などの各種内規も労務の守備範囲。

法改正や社会情勢の変化に応じて規則や規定を変更するケースもあります。
規則や規程の変更にあたっては、経営陣や労働組合(または従業員代表)との協議や同意の取り付けが必須。相手を説得するだけの理解力が欠かせません。そのため、労務担当には規則規定に関する幅広い知識が求められます。
\認定講習で取得できる!人事総務検定/
勤怠管理の知識

労務担当に必要な基礎知識2つ目は、勤怠管理に関する知識です。勤怠管理の知識が必要な理由は以下のとおり。
✔ 適切な給与計算や未払防止のため
✔ 時間外労働を適切に管理するため
✔ 変形労働時間制等を運用するため
労務担当は、社全体の勤怠データを収集・チェックしています。
【労務担当がチェックするポイント】
✔ 申告時間と実労働時間に乖離がないか
✔ 36協定に違反する時間外労働がないか
✔ 年休等を適切に取得しているか…etc.
労務担当が勤怠データを収集する理由は、従業員の労働時間を正しく把握し、適切な給与計算や未払防止につなげるためです。

過重労働防止の観点から従業員の残業時間も厳しくチェック!
フレックスタイム制や変形労働時間制を導入している場合、各部署が正しく運用しているか就業状況を抜き打ちでチェックするなど、社全体の勤怠管理を担っています。

とりわけ、以下の勤務体系を採用している場合はチェックを厳格化。
■ 日・週単位のシフト制
■ フレックスタイム制
■ 月・年単位の変形労働時間制
上記の勤務体系は、季節的な業務の繁閑等に対応しやすい反面、日・週・月の労働時間が変則的で管理ミスが起きやすいからです。
ほかにも年次有給休暇を適切に取得しているか、代休や振替休日の取り忘れはないか、従業員のワークライフバランスも定期的にチェック。必要に応じて、対象者本人や管理職者へ取得状況を通知したり、指導したりするケースもあります。
そのため、労務担当には勤怠管理の専門的知識が求められます。
\講習受講で取得!労働時間適正管理者検定/
給与計算の知識
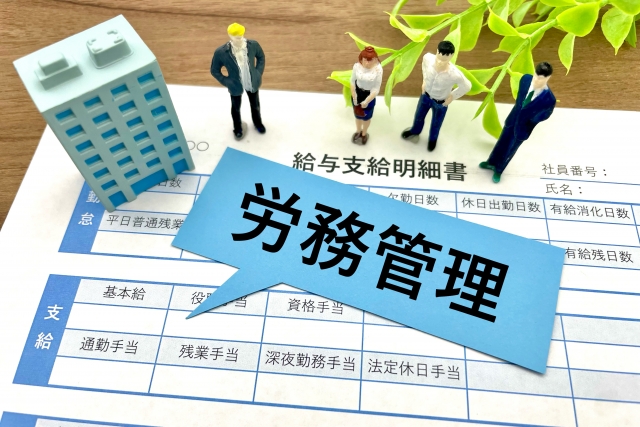
労務担当に必要な基礎知識3つ目は給与計算。労務に給与計算の知識が求められる理由は以下のとおりです。
✔ 保険料や税金を正しく算出するため
✔ 給与計算の仕組みを理解するため
✔ 法律に則って賃金を支払うため
給与計算は手順があらかじめ決まっています。
1:勤怠締め処理
2:控除額の算出①
└不就労分(遅刻・早退・欠勤など)
3:総支給額の決定
4:控除額の算出②
└社会保険料、税金
5:差引支給額の決定
6:支給手続き
└給与明細や賃金台帳の作成、振込
7:社会保険料や税金の納付
保険料や税金を正しく算出するため、上記の流れに沿って計算しなければなりません。また従業員へ支払う給与額(手取り)は、以下の方法で算出されます。
総支給額-控除額=給与額(手取り)

総支給額と控除額の内訳はこちら。
〇総支給額(基準内給与+基準外給与)
└基準内:基本給+毎月固定の手当 ※1
※1 役職手当、住宅手当など
└基準外:毎月変動する手当 ※2
※2 時間外手当、休日手当など
〇控除額(法定控除+その他控除)
└法定控除:税金(所得税、住民税)、
雇保、健保、厚保の各保険料
└その他控除:組合費や財形貯蓄など
給与額は働いた時間だけで決まるわけではありません。基本給のほか、各種手当や控除額を含めて算出されます。企業によって取扱いが異なる部分もあるため、その仕組みは意外と複雑です。

賃金支払いの5原則の理解も必須。
・通貨払いの原則
・直接払いの原則
・全額払いの原則
・毎月1回以上の原則
・一定期日払いの原則
労働者への賃金支払は、上記の原則に則ることが法律で義務付けられているからです。給与計算に携わる方は、付帯知識としておさえておく必要があります。
これらの観点から、労務担当には給与計算の専門知識が求められます。
\講習受講で取得!人事総務検定 給与計算技能/
労働保険・社会保険の知識

労務担当に必要な基礎知識4つ目は、労働保険と社会保険に関する知識です。労働保険と社会保険の知識が必要な理由は以下のとおり。
✔ 手続きの頻度が多い
✔ 公的機関とやりとりが発生する
✔ 手続きでトラブルになる場合がある
労働保険・社会保険に関する手続きは、労務のなかでもとりわけ頻度が多い業務。労災の申請や離職票の発行、入退職に応じた加入脱退など、随時手続きが発生します。
手続きでは、労災保険が労働基準監督署、雇用保険はハローワーク、健康保険と厚生年金は年金事務所と、管轄の公的機関へそれぞれ届け出。届出内容について各機関とやりとりする機会も多く、ある程度の知識を備えておかねばなりません。

手続きにあたり思いがけないトラブルに発展する事もあります。
<トラブルの例>
✔ 退職理由への異議申し立て
✔ 保険証の発行が遅れる
✔ 保険料の未納が発生する
トラブルが起きやすい手続きの一つは、雇用保険の離職票発行。退職理由をきちんと確認せずに作成すると、退職者から異議申し立てを受ける場合があります。

「会社都合」の退職なのに、退職理由の欄に「自己都合」と記載されたなど
なお離職票の退職理由を変更した場合、退職者の雇用保険給付や企業の助成金に影響が出ます。
<離職票の退職理由変更に伴う影響>
・退職者本人
雇用保険の求職者給付
└給付制限期間や受給期間が変わる
・企業
雇用関連の助成金
└不支給となる場合がある
そのため離職票の作成にあたっては、社員から退職届を提出させたり、雇用保険給付の仕組みを事前に説明したりするなどの工夫が求められます。
ほかにも社会保険の加入手続きを怠ると健康保険証の発行が遅れたり、保険料未納による追加徴収が発生したりと様々なトラブルにつながるリスクがあります。
以上の観点から、労務担当には労働保険・社会保険の基礎知識が求められます。
\社労士対策におすすめのオンライン予備校/
労働契約の知識

労働契約の知識も労務担当には欠かせません。主な理由は以下のとおり。
✔ 雇用契約書を作成するため
✔ 雇用契約を取り交わすため
✔ 雇用契約を管理更新するため
労務担当は会社と従業員との労働契約を管理する役割を担っています。入社や契約更新にあたって労働条件通知書や雇用契約書を作成します。

書類作成~労働条件の提示、契約締結までワンストップで対応。
対象者は正社員だけでなく、嘱託社員や契約社員、パート・アルバイトまで全社員に及びます。有期契約(嘱託や契約)の場合、数か月~1年で雇用契約が満了するため、手続き頻度が多いのが特徴です。

とりわけ労働契約で重要なのは「労働基準法」と「労働契約法」。
両者の違いと労働契約上の具体的な定めは以下のとおりです。
労働基準法:
労基署の指導対象となる内容を規定
労働契約法:
争い事防止の民事上のルールを規定
| 項目 | 労働基準法 | 労働契約法 |
|---|---|---|
| 契約締結 | ・労働条件は書面で明示 ・有期労働契約は上限3年 ※以下の場合は上限5年 └専門知識を有する業務 └60歳以上の労働者 | ・就業規則の内容をもって労働条件とする ※合理的かつ労働者への周知が前提 ・契約期間を短くしないよう配慮する |
| 契約変更 | ・就業規則を下回る変更は 不可 | ・労使双方の合意が必要 ・使用者が一方的に就業規則を変更しても 労働者に不利な変更は認めない ・就業規則により労働条件を変更する場合 合理的かつ労働者への周知を条件とする |
| 契約終了 | ・解雇は30日前までに予告 └予告が無い場合、 解雇予告手当を支払う | ・合理性なく社会通念上認められない場合 無効 ・やむを得ない場合を除き、契約期間満了 までは解雇不可 |
契約のフェーズによって定める内容が異なるのが注意点。それぞれの場面で法に則って対応するためにも、労務担当は労働契約の知識が必要です。
\労働法務士が学べるオンライン予備校/
安全衛生の知識

労務担当に必要な基礎知識6つ目は、安全衛生に関する知識。理由は以下のとおりです。
✔ 安全な職場環境を構築するため
✔ 健診やストレスチェックのため
✔ 産業医や保健師と連携するため
企業は労働安全衛生法によって、安全衛生管理を通じて従業員の健康の保持増進に努めることが求められています。その中心的な役割を果たすのが「労務」。労働災害防止の計画策定や管理体制の構築、職場巡視など、職場の安全衛生に関する幅広い業務に携わっています。

従業員の健康診断やストレスチェックも業務の範疇。
従業員数が50人以上の事業所では、健康診断やストレスチェックの結果を集約して労働基準監督署への報告も行います。
過重労働防止の観点から、長時間労働者のケアも労務の役割です。従業員の勤怠データをもとに、時間外労働や休日労働時間が一定の基準を超える者を抽出し、産業医による面接指導を実施。安全衛生委員会でその後の対応を審議するなど、時間外労働の削減につなげています。
これらの業務に対応するためにも、労務担当には安全衛生の知識が求められます。
\衛生管理者が学べるオンライン予備校/
労務トラブル対応の知識

労務担当に必要な基礎知識7つ目は労務トラブル対応に関する知識。理由は以下のとおりです。
✔ 様々な労務トラブルに対応するため
✔ 初動対応を誤らないため
✔ 経営リスクへの発展を防ぐため
労務は、社内トラブルの対応窓口としての役割を担っています。労働契約の不利益変更や賃金未払いなど、会社と従業員間のトラブルはもちろん、職場でのいじめやハラスメントなど内容は様々。

事態を悪化させないために適切な初動対応が求められます。
賃金未払いを訴える社員が出た場合、初動対応が遅れたり、話を聞く機会を設けなかったりすると従業員が労働局へ通報するケースがあります。

通報が入ると、労働基準監督署が査察などの名目で検査に入ることも…。
出退勤の記録や賃金台帳を確認され、賃金の未払いがあったと認定された場合、過去にさかのぼって残業代などを支給しなければなりません。
当該社員だけでなく社全体での調査を命じられるため、企業規模によっては数百万、数千万円以上の支払いが発生する事態となります。状況に応じて企業名が公表されたり、メディアが取り上げたりするなど、経営リスクに発展する可能性も否めません。
こういった事態を防ぐためにも、労務担当は労務トラブル対応の知識が求められます。
\ハラスメントアドバイザーが学べる予備校/
まとめ
以上、労務担当に必要な基礎知識7選を解説しました。

労務は法に基づく業務が大半を占めるなど専門知識が求められる部署です。
労務の仕事で行き詰まったり、知識不足を感じたりする方は、業務に応じて必要な知識を身に付けましょう。
別記事で「人事労務におすすめの資格16選」を紹介しているので、気になる方はこちらもどうぞ。