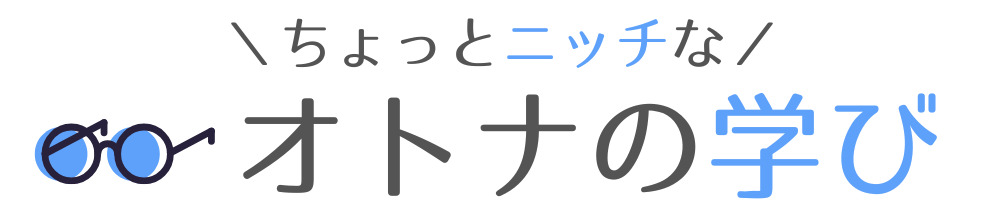MBA取得や学び直しのため大学院進学を検討する方は、こんな悩みはありませんか?
・大学院入試で準備する書類が分からない
・履歴書や研究計画書の書き方が知りたい
準備が面倒で二の足を踏む方も多い大学院入試。

出願に必要な書類と書き方をおさえておけば、焦らずに済みます。
この記事では、大学院入試の出願に必要な書類をまとめて紹介します。自身の進学経験を元にした内容なので、大学院入試の出願を検討する方は、ぜひ参考にしてみてください。
\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/
大学院の出願書類と準備期間
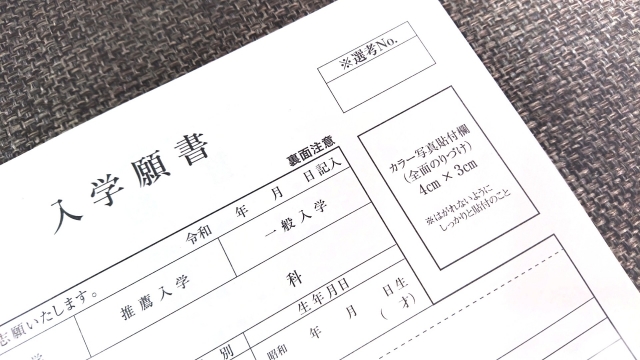
大学院入試の出願には色々な書類が必要です。
自分で作成する書類のほか、出身大学や勤務先に発行してもらう書類もあります。

大学院への出願に必要な書類はこちら
<自分で作成するもの>
〇入学願書
〇履歴書
〇職務経歴書
〇研究計画書
〇志望理由書/エッセイ
<他者に発行してもらうもの>
〇大学の卒業証明書
〇大学の成績証明書
〇語学検定の成績
〇推薦書
〇企業の在籍証明書
まず作成しなければならないのが「入学願書」です。大学院から郵送で取り寄せるか、ホームページから様式をダウンロードして作成。大学院によっては「履歴書」を兼ねる場合もあります。
「職務経歴書」は、大学院の指定様式がある場合はそれに沿って作成。指定がない場合は任意様式でオーケーです。

大学院入試でもっとも大事な書類が「研究計画書」。
口述試験にて内容を問われるため、時間をかけて丁寧に作成しましょう。「志望理由書」や「エッセイ」も同様です。

他者に発行してもらう書類は、大学の「卒業証明書」と「成績証明書」。
大学の事務窓口へ直接取りに行く場合と、郵送で取り寄せる場合の2パターンがあります。
TOEFL®やTOEIC®といった語学検定の成績が必要な場合は、各団体から発行されたスコアシートを提出。勤務先の「推薦状」や「在籍証明書」を求める大学院もあります。
発行に時間がかかる書類もあるので、提出期日に間に合うよう余裕をもって手配しましょう。

参考に、私が大学院入試の出願準備に要した期間がこちら。
<大学院入試の出願準備に要した期間>
〇入学願書(履歴書)…1週間
〇職務経歴書…1週間
〇研究計画書…4週間
└研究テーマの選定に2週間
└研究計画書の執筆に2週間
準備に要した期間:計6週間
私の場合、大学の卒業証明書と成績証明書は母校の事務窓口へ直接赴いて入手しました。

職務経歴書は直近の転職活動時に作成したものを一部修正して代用。
出願準備に要した期間はおよそ6週間でした。
大学院入試の履歴書等の書き方
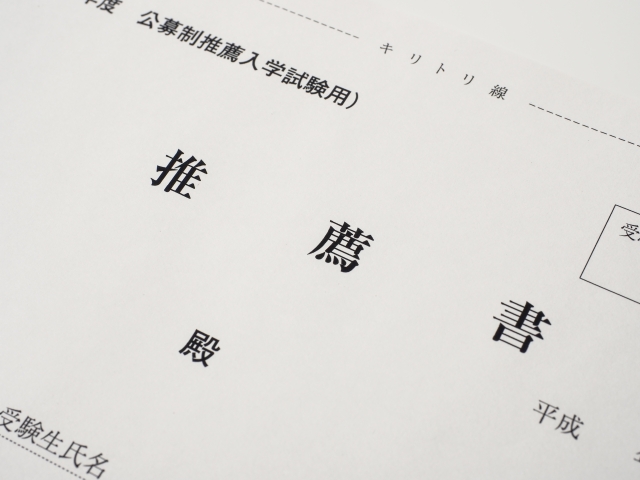
履歴書
大学院入試の履歴書は「わかりやすさ」を重視しましょう。これまでの学歴や仕事上の経験で誇れる実績や成果はしっかりアピール。自分の経験やスキルは、出願先の大学院や研究科に合わせてアレンジするのがポイントです。

自己PR欄では、研究を通じてどんな貢献ができるかを記入します。
大学院入試で未経験の分野に応募する際は、研究に対する熱意や興味を示すことも重要。何故その研究に興味があるのか、研究を通じてどのように成長したいと考えているのかを明確に伝えられるかがポイントです。

仕事の経験や獲得スキルなど、研究に関連する能力や経験を記入しましょう
大学院入試では「逆時系列式」の履歴書を勧めるサイトもありますが、必ずしも逆時系列である必要はありません。履歴書のフォーマットを用意している大学院も多いので指定された様式に沿って作成します。
なお、大学院入試で職務経歴書が求められるかは「研究科」や「プログラム」により異なります。一般的に、MBAなどの専門職プログラムにおいて職務経歴書の提出を求めるケースが多いです。
研究計画書
大学院入試の出願書類で最重要なのが「研究計画書」です。研究に比重を置く大学院の場合、提出は必須。MBAなど実務教育に比重をおく大学院は「志望理由書」や「エッセイ」を提出させるケースもあります。

研究計画書の基本的要素は以下の5つ
<研究計画書の基本要素>
・研究テーマ
・問題意識
・研究目的
・研究方法
・参考文献
上記のほか、これまでのキャリアや志望理由、大学院修了後の計画を記述させる場合もあります。
社会人はビジネス経験を元にした問題意識を示し、その課題を解決したい理由を明確にしなければなりません。どんな方法で研究するのか、研究の成果を今後のキャリアにどう活かすのか、ストーリー性を持たせることも重要です。

研究精度はあまり神経質にならなくてオーケー。
研究計画は、入学後に教授の指導を受けながら修正していくものだからです。それよりも、研究の目的や自分の考えを論理的に伝える力が求められます。
合格の秘訣は「研究テーマを小さく絞る」こと。背伸びせず、在学中に達成可能な研究テーマや手法を示めるかがポイントです。
職場が抱える仕事上の問題を2~3個取り上げ、それを解決するため○○を研究するという建付けがおすすめ。日頃から「職場が抱える問題」と「その要因」を意識しておきましょう。

参考に、私が使用した研究計画書作成の指南書はこちら。
<研究計画書作成で使用した指南書>
題名:大学院に合格できる!
研究計画書 書き方実践講座
著者:工藤 美知尋 氏
発行:ダイヤモンド社
気になる方は以下のリンクからご確認ください。
\【PR】楽天ブックスから購入できます/
 | 大学院に合格できる!研究計画書書き方実践講座 [ 工藤美知尋 ] 価格:3,850円 |
志望理由書・エッセイ
志望理由書やエッセイは、自分のキャリアプランと大学院の志望理由をまとめた書類。社会問題に関する問題意識を問われる場合もあります。

志望理由書に記述する内容はこちら。
<志望理由書に記述する内容>
・これまでのキャリアと実績
・現在の業務内容
・仕事を通して培った強み
・当該分野を学びたい理由
・当該大学院を志望する理由
・修了後のキャリアプラン
上記項目を中心に記述させるケースが多く、文章としてまとめるケースもあれば、項目別に記述させるケースもあります。

文字数は800~1,500文字程度と大学院によってまちまち。
冗長にならずに、伝えたいことを簡潔にまとめるのがポイントです。
大学院によっては、これまでのキャリアと修了後のキャリアプランを提出させる場合もあります。過去の業務経験を棚卸しして、自分のキャリアと志望動機を一連のストーリーにまとめましょう。
卒業証明書・成績証明書
大学の「卒業証明書」と「成績証明書」は大学院入試の出願における必須書類。

母校の事務窓口で入手するか、郵送で取り寄せる形になります。
即日発行できなかったり、郵送対応していなかったりする大学もあるので注意しましょう。複数の大学院を併願する場合は、出願数に応じて証明書の原本を取り寄せる必要があります(コピー不可のため)。
そのため、卒業証明書と成績証明書は、志望校が決まった段階で早めに入手しておきましょう。
推薦書
社会人が大学院入試を受ける場合、上司の推薦書を求められるケースもあります。

推薦書は、客観的な人物評価や大学院進学の適正などを記述するもの。
職場の上司に、いきなり「推薦書を書いてください」とお願いしても相手が戸惑ってしまうので、予め大学院の志望理由を伝えて進学の目的を理解してもらうことが大切です。

書き方が分からない上司も多いので、記入例を入手して渡すのがおすすめ。
ちなみに、推薦書には「自己推薦書」なるものもありますが、こちらは自分で執筆するもの。志望理由書の書き方をベースに自分の強みを強調して記述しましょう。
おすすめの出願時期は秋入試

ここまで大学院入試の出願準備について解説しました。「準備するものは分かった。だけど、いつ出願するのが良いのだろう…」と思う方もいるでしょう。その答えは「秋入試」です。

理由は、秋入試で失敗しても春入試で再度挑戦できるから!
大学院入試の時期は、9~11月の秋入試と翌1月末~2月の春入試に分かれます。
入学時期はいずれも翌4月。春入試を狙って不合格となった場合、次に挑戦できるのは次年度の秋入試(9月以降)になってしまいます。入学時期は丸1年遅れる形となるため、多くの社会人は次の受験を諦めてしまいます。
一方、秋入試は不合格だったとしても次の春入試までの期間は短くて2か月、長くても4~5か月で済みます。

春の入試で合格できれば、入学時期は秋入試の合格者と同じ4月です。
不合格時のリスクヘッジに加え、モチベーションを維持しやすい点からも、まずは秋入試を目指すことをおすすめします。
なお、9月入学制度がある大学院は夏も入試を行います。以下の記事で入試時期の詳細を解説しているので気になる方はこちらもどうぞ。
まとめ
以上、大学院入試における出願書類と準備期間について解説しました。

社会人の大学院受験は「秋季入試」がおすすめ。
万が一不合格になっても、春入試で再チャレンジできるからです。
出願書類は準備に時間がかかるものもあるので、入試時期から逆算して準備しましょう。
\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/