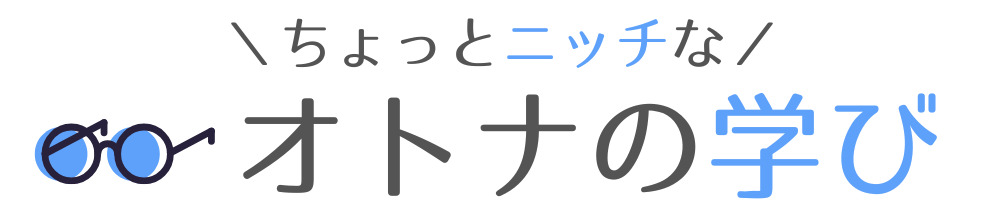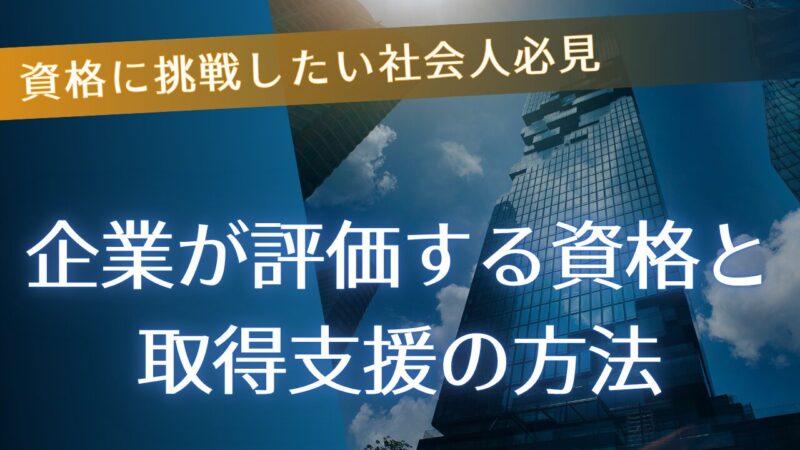本ページにはプロモーションが含まれています。
スキルアップを目指して資格や検定に挑戦しようと考える方は、こんな悩みはありませんか?
✔ 企業は資格を評価しているのか
✔ どの部署で何の資格が求められるのか
✔ 資格取得は人事評価に影響があるのか
じつは仕事に関連する「資格」を評価する企業は沢山あります。そこで本記事では、企業における資格取得の評価について解説します。

記事を読むメリットは以下のとおり。
〇 資格を評価する企業の特徴がわかる
〇 部署ごとに評価の高い資格がわかる
〇 資格取得による人事への影響がわかる
具体的には、(独)労働政策研究・研修機構の「企業における資格・検定等の活用に関する調査」データをもとに、業種別・規模別にみた資格への評価や取得後の措置について紹介。

常用雇用者100人以上の企業1,465社(農林漁業と公務を除く)の回答をベースにしているため、業種や規模別の資格に対する評価が分かります。
\多彩な資格講座を揃えるオンライン予備校/
企業は資格を評価している

結論からいうと、大半の日本企業は仕事に関連する「資格」を評価しています。仕事のスキルアップによる生産性の向上や対外的な能力アピールにつながることが理由です。
実際、労働政策研究・研修機構が2014年に行った「企業における資格・検定等の活用に関する調査」では、企業が従業員に対して資格取得を奨励したり、人事評価に反映したりしている状況が明らかになりました。
以下、上記の調査をもとに、企業の資格や検定に対する評価の具体的な中身を解説します。
評価対象となる資格
労働政策研究・研修機構の「企業における資格・検定等の活用に関する調査」では、評価の対象となる資格・検定を58種類列挙し、その中から重要なものを5つ選択させる形を取っています。
<調査における資格・検定の選択肢>
◇代表的な資格・検定:56種類
◇社内資格・検定:1種類
◇上記以外の資格・検定:1種類
計58種類
本記事では便宜上、上記の中から管理部門に関連する資格と「社内資格・検定」を合わせた以下の10種類を紹介。
◇管理部門に関連する資格(9種類)
・安全管理者
・衛生管理者
・ITパスポート
・MOS
・語学検定(英検、TOEIC、TOEFL)
・簿記
・FP
・中小企業診断士
・社会保険労務士
◇各社の社内資格・検定
それぞれの資格につき「重視する」と回答した企業の数を、調査に参加した企業総数(業種別・規模別)で割って出た値をパーセント(%)で表記します。
業種別にみた資格の評価
常用雇用者100人以上の企業1,465社(農林漁業と公務を除く)の「業種別」における資格の評価は以下のとおり。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/業種別の企業数×100
※緑太字:評価割合が3割以上
| 資格/業種 | 建設 | 製造 | 電気 ガス 熱供給 水道 | 情報 通信 | 運輸 | 卸売 小売 | 金融 保険 不動産 | 飲食 宿泊 | 医療 福祉 | 教育 及び 学習 支援 | サービス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 7.2 | 24.7 | 8.3 | 0.0 | 29.5 | 5.5 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 7.1 | 7.5 |
| 衛生管理者 | 17.5 | 45.6 | 33.3 | 6.1 | 52.7 | 23.0 | 8.5 | 32.9 | 2.4 | 17.9 | 25.1 |
| ITパスポート | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 22.4 | 0.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 3.0 |
| MOS | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 16.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.6 | 1.5 |
| 語学検定 | 2.1 | 12.9 | 8.3 | 12.2 | 6.2 | 3.9 | 2.1 | 13.7 | 0.0 | 3.6 | 9.7 |
| 簿記 | 18.6 | 12.1 | 8.3 | 20.4 | 8.5 | 14.1 | 34.0 | 19.2 | 7.3 | 14.3 | 10.1 |
| FP | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 中小企業診断士 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 社会保険労務士 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.3 | 3.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 社内資格・検定 | 2.1 | 9.0 | 0.0 | 4.1 | 3.1 | 15.6 | 14.9 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
調査では「衛生管理者」が4つの業種で評価割合3割を超える結果となりました。とりわけ「製造業」では4割超、「運輸業」にいたっては5割超の企業が評価すると回答しています。
次いで評価が高かったのが「簿記」と「FP」。どちらも「金融・保険・不動産業」の業種で、評価割合が3割を超えました。

3割に届かなかったものの比較的高い評価を得たのが「安全管理者」。
労働安全衛生法で有資格者の中から選任が義務付けられていることも相まって、「製造業」と「運輸業」でそれぞれ2割以上の評価を得ています。
そのほか「情報通信業」では「ITパスポート」の評価が2割を超えるなど、業種によって評価する資格が異なることが伺えます。
規模別にみた資格の評価
一方、常用雇用者100人以上の企業1,465社(農林漁業と公務を除く)の「規模別」における資格の評価は以下のとおりです。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/規模別の企業数×100
※緑太字:評価割合が3割以上
| 資格/従業員数 | 100~ 299人 | 300~ 499人 | 500~ 999人 | 1000人 以上 |
|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 14.1 | 13.5 | 10.5 | 11.2 |
| 衛生管理者 | 31.7 | 38.5 | 32.9 | 39.9 |
| ITパスポート | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 5.1 |
| MOS | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 0.6 |
| 語学検定 | 6.6 | 10.9 | 9.9 | 19.7 |
| 簿記 | 13.4 | 14.7 | 15.8 | 12.9 |
| FP | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 3.9 |
| 中小企業診断士 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.4 |
| 社会保険労務士 | 3.2 | 3.2 | 5.3 | 2.8 |
| 社内資格・検定 | 4.6 | 6.4 | 10.5 | 20.8 |
規模別にみると「衛生管理者」の資格がすべての規模で3割を超える評価となりました。業種別の評価と同様、法規対応の観点から、有資格者へのニーズが高いことが伺えます。

ビジネスの必須スキル「簿記」は、規模を問わず評価割合が10%超え。
そのほか「語学検定」と「社内資格・検定」は、企業規模が大きくなるほど、評価割合が高くなる傾向が示されました。
\抜群のコスパと豊富な合格実績/
企業が資格を評価する理由

ここまで業種や規模による差はあるものの、多くの企業が資格を評価していることを解説しました

では具体的にどんな理由で資格を評価しているのでしょうか?
以下、労働政策研究・研修機構の「企業における資格・検定等の活用に関する調査」において、企業が資格を評価する理由をまとめたものです。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/各理由を選んだ企業数×100
※重視する理由は「複数回答可」
※緑太字は資格ごとに最も高かった割合
| 資格/理由 | 知識 技能 (基礎) | 知識 技能 (業務) | 知識 技能 (全般) | キャリア 形成 | 法規 対応 | 業界 取引 | 対外的な アピール | 企業内の 能力評価 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 26.2 | 51.3 | 18.5 | 11.3 | 70.8 | 6.2 | 1.5 | 4.1 | 1.0 |
| 衛生管理者 | 26.9 | 51.8 | 18.3 | 15.1 | 78.1 | 2.4 | 1.9 | 5.8 | 0.9 |
| ITパスポート | 61.5 | 56.4 | 28.2 | 10.3 | 0.0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 0.0 |
| MOS | 47.6 | 61.9 | 4.8 | 14.3 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 9.5 | 0.0 |
| 語学検定 | 34.8 | 47.7 | 25.8 | 50.0 | 0.0 | 14.4 | 19.7 | 18.9 | 7.6 |
| 簿記 | 55.7 | 73.1 | 23.9 | 26.9 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 13.4 | 1.0 |
| FP | 46.2 | 65.4 | 57.7 | 23.1 | 0.0 | 3.8 | 34.6 | 15.4 | 0.0 |
| 中小企業診断士 | 35.0 | 75.0 | 55.0 | 50.0 | 0.0 | 5.0 | 35.0 | 5.0 | 0.0 |
| 社会保険労務士 | 31.0 | 78.6 | 38.1 | 35.7 | 16.7 | 0.0 | 9.5 | 11.9 | 4.8 |
| 社内資格・検定 | 56.9 | 67.2 | 34.5 | 27.6 | 2.6 | 8.6 | 21.6 | 47.4 | 2.6 |
調査の結果、企業が資格を評価する理由は以下の3タイプに分けられます。
①知識・技能習得型
②法規対応型
③キャリア形成寄与型
資格を評価する一つ目のタイプは「知識・技能習得型」。ビジネスの基礎知識や業務で必要なスキルを習得すれば、生産性の向上が見込めることが評価の理由です。

「知識・技能習得型」で高評価の資格は以下のとおり。
①知識・技能習得型
ITパスポート、MOS、簿記、FP、中小企業診断士、社労士、社内資格・検定
企業が資格を評価する二つ目のタイプは「法規対応型」。企業では、業種や規模に応じて社内に特定の有資格者を配置することが法律上義務付けられているケースがあります。

「法規対応型」で評価の高い資格は以下の2つ。
②法規対応型
安全管理者、衛生管理者
安全管理者は、法定業種のうち常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、有資格者の中から選任しなければなりません。衛生管理者についても、労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する場合に選任が義務付けられています。
資格が評価される三つ目のタイプは「キャリア形成寄与型」。将来的にグローバル市場を担当したり、海外赴任したりと中長期的なキャリア形成を図る観点から評価されます。

「キャリア形成寄与型」で評価の高い資格はこちら。
③キャリア形成寄与型
語学検定(英検、TOEIC、TOEFLなど)
語学検定以外にも、中小企業診断士が5割、社会保険労務士で3割超の企業が評価すると回答。難関資格の取得も、キャリア形成に寄与する傾向の高いことが伺えます。
\難関資格合格のための通信講座/
資格を評価する部門

次に、企業の中で資格に対する評価の高い部門を紹介します。

労働政策研究・研修機構による調査の結果は以下のとおり。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/各部門を選んだ企業総数×100
※調査では最も重視する部門を1つだけ選択
※緑太字は資格ごとに最も高かった割合
| 資格/部門 | 管理 事務 | 経営 企画 | 法務 | 経理 財務 | 広報 宣伝 | 情報 システム 関連 | 営業 販売 | 購買 物流 | 研究開発 設計 デザイン | 製造 | 運輸 | 建設 | その他 | 会社 全体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 28.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 32.8 | 9.2 | 2.1 | 2.1 | 12.3 |
| 衛生管理者 | 46.2 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 0.2 | 0.2 | 14.0 | 3.4 | 0.4 | 3.7 | 20.9 |
| ITパスポート | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.7 | 17.9 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |
| MOS | 28.6 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 38.1 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 14.3 |
| 語学検定 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 8.3 | 65.2 |
| 簿記 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 14.9 |
| FP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.6 |
| 中小企業診断士 | 10.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 社会保険労務士 | 54.8 | 0.0 | 11.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 19.0 |
| 社内資格・検定 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 23.3 | 0.0 | 2.6 | 23.3 | 1.7 | 0.0 | 10.3 | 34.5 |
企業の部門別でみると「管理事務」で評価が高かったのは「衛生管理者」と「社会保険労務士」。衛生管理者は、職場の衛生環境を維持管理するため、有資格者の配置が法律で義務付けられていることが高評価の理由です。
社会保険労務士は、就業規則の作成や従業員の勤怠管理、社会保険の手続きなど、管理部門の中核として活躍できる資格。さまざまな業務にスキルを活かせるため、評価が高いと考えられます。

「経理財務」は「簿記」、「営業販売」では「FP」の評価がダントツ。
そのほか情報システム部門では「ITパスポート」「MOS」の評価が高いなど、部門によって求められる資格に偏りがあることが示されました。
\認定講習で取得!LECの人事総務検定/
企業が有資格者を確保する方法

ここまで企業が資格を評価していること、業種や規模、部門によって重視する資格が異なることを解説しました。

では、企業はどんな方法で有資格者を確保しているのでしょうか?
労働政策研究・研修機構による調査結果は以下のとおりです。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/各方法を選んだ企業数×100
※確保の方法については「複数回答可」。
※緑太字は資格ごとに最も多かった割合。
| 資格/確保の方法 | 業務 命令 | 取得 奨励 | 自己 啓発 | 採用 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 64.6 | 26.2 | 13.8 | 5.6 | 3.6 |
| 衛生管理者 | 60.6 | 23.7 | 23.0 | 8.0 | 5.6 |
| ITパスポート | 23.1 | 23.1 | 64.1 | 2.6 | 0.0 |
| MOS | 19.0 | 19.0 | 76.2 | 14.3 | 9.5 |
| 語学検定 | 6.8 | 23.5 | 74.2 | 17.4 | 2.3 |
| 簿記 | 13.9 | 23.4 | 57.2 | 26.4 | 2.0 |
| FP | 3.8 | 34.6 | 69.2 | 0.0 | 3.8 |
| 中小企業診断士 | 0.0 | 5.0 | 85.0 | 10.0 | 5.0 |
| 社会保険労務士 | 2.4 | 9.5 | 73.8 | 14.3 | 7.1 |
| 社内資格・検定 | 33.6 | 41.4 | 25.0 | 2.6 | 12.1 |
上記から、企業が有資格者を確保する方法は、おおむね2タイプに分けられます。
①会社主導型
②取得奨励型
企業が有資格者を確保する一つ目のタイプは「会社主導型」。業務命令を通じて、従業員に資格を取得させるパターンになります。

有資格者の配置が法律で義務化されている場合によくあるケース。
「会社主導型」に該当するのは、業務命令での取得が多い「安全管理者」と「衛生管理者」の2資格になります。
有資格者確保のタイプ二つ目は「取得奨励型」。昇進や昇格、長期的なキャリア形成の観点から、従業員自らが資格取得に励むよう企業が促すパターンです。
上記の調査では、「取得奨励」と「自己啓発」の回答が最も多かった以下の資格が該当します。
<取得奨励が最も多い>
〇社内資格・検定
<自己啓発が最も多い>
〇ITパスポート、MOS、語学検定、簿記、FP、中小企業診断士、社労士
「社内資格・検定」は、取得奨励型の中でも企業主導の性格が強く、一定の職位まで(あるいは職位ごと)に取得を奨励するケースが多いです。そのため、業務命令に近い性質の資格といえます。
そのほかの資格は、取得の有無を従業員の意思にゆだねる性質が強く、自己啓発として推奨する資格。昇進や昇格には直結しないものの、仕事の生産性向上に寄与する資格といえます。
資格取得の支援方法

上記では、企業が有資格者を確保する方法を紹介しました。

では、企業は資格取得に対してどんな支援をしているのか。
労働政策研究・研修機構による調査結果は以下のとおりです。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/各方法を選んだ企業数×100
※支援の方法は「複数回答可」。
※緑太字は資格ごとに最も多かった割合。
| 資格/支援方法 | 費用 援助 | 時間的 配慮 | 勉強会 開催 | 特に なし |
|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 86.7 | 41.0 | 4.1 | 5.6 |
| 衛生管理者 | 86.5 | 40.4 | 3.2 | 7.7 |
| ITパスポート | 87.2 | 12.8 | 10.3 | 12.8 |
| MOS | 66.7 | 19.0 | 0.0 | 28.6 |
| 語学検定 | 63.6 | 21.2 | 15.9 | 22.7 |
| 簿記 | 44.8 | 21.4 | 9.0 | 39.8 |
| FP | 50.0 | 15.4 | 7.7 | 38.5 |
| 中小企業診断士 | 70.0 | 15.0 | 10.0 | 20.0 |
| 社会保険労務士 | 38.1 | 9.5 | 0.0 | 54.8 |
| 社内資格・検定 | 37.1 | 21.6 | 51.7 | 11.2 |
上記から、従業員への資格取得の支援の在り方は3つのタイプに分けられます。
①費用援助型
②時間配慮型
③勉強会型
資格取得の支援一つ目は「費用援助型」。従業員の資格取得に際して、受験料やテキスト代、講習費用などを援助するタイプです。「費用の援助」の回答が最も多かった以下の資格が該当します。
①費用援助型
安全管理者、衛生管理者、ITパスポート、MOS、語学検定、簿記、FP

支援方法の二つ目は「時間配慮型」。
受験にあたり、業務負担を減らしたり、受験日の仕事を休みにしたりするタイプです。上記すべての資格が対象となりますが、ニーズの高い資格ほど時間的配慮の割合も高くなっています。
資格取得の支援三つ目は「勉強会型」。社内で、試験対策の勉強会を開催するタイプになります。「勉強会の開催」の回答が最も多かった「社内資格・検定」が該当します。
資格取得の支援対象

次に、企業が資格取得を支援する対象者について解説します。労働政策研究・研修機構による調査結果は以下のとおり。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/各対象を選んだ企業数×100
※支援対象はいずれか1つを選択。
※緑太字は資格ごとに最も多かった割合。
| 資格/支援対象 | 全員 | 正社員 のみ | 非正規 のみ | 支援 なし |
|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 15.9 | 78.5 | 0.0 | 3.1 |
| 衛生管理者 | 18.3 | 76.3 | 0.0 | 3.7 |
| ITパスポート | 20.5 | 71.8 | 0.0 | 0.0 |
| MOS | 14.3 | 66.7 | 0.0 | 12.9 |
| 語学検定 | 31.8 | 50.0 | 0.0 | 15.2 |
| 簿記 | 20.9 | 52.2 | 0.0 | 24.4 |
| FP | 23.1 | 46.2 | 0.0 | 26.9 |
| 中小企業診断士 | 25.0 | 65.0 | 0.0 | 10.0 |
| 社会保険労務士 | 14.3 | 47.6 | 0.0 | 35.7 |
| 社内資格・検定 | 37.9 | 56.0 | 0.0 | 2.6 |
上記の調査では、大半の企業が「正社員のみ」を資格取得の支援対象とすることが分かりました。
しかしながら正社員のみを対象とする支援は、2019年に施行された政府主導の「働き方改革」によって、現在では非正規にも広がっているものと考えられます。
働き方改革では「同一労働同一賃金ガイドライン」を定め、正規と非正規の不合理な待遇格差の是正を企業に求めているからです。

不合理な待遇格差には、キャリア形成および能力開発も含まれます。
従業員のキャリア形成や能力開発として資格取得の支援を掲げた場合、非正規を対象から外すには「合理的な理由」がなければなりません。そのため現在の資格取得支援は、非正規も含めた従業員全体へ広がっているものと推定されます。
\多彩な受講スタイルが選べる資格の予備校/
資格取得者への措置(褒美)

最後に、資格を取得した従業員に対する人事管理上の措置について解説します。

人事管理上の措置とは、いわば資格の取得に対する「褒美」。
従業員の労をねぎらい、モチベーションアップにつなげたり、人材流出の防止につなげたりするのが目的です。労働政策研究・研修機構による調査結果は以下のとおり。
評価割合(%)=「重視する」と回答した企業数/各措置を選んだ企業数×100
※人事管理上の措置は「複数回答可」。
※緑太字は資格ごとに最も多かった割合。
| 資格/措置 | 昇進 昇格 | 配置 異動 | 昇給額 昇給率 | 資格 手当 | 一時金 | 賞与 上乗せ | 表彰 掲示 | 特に なし |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全管理者 | 28.2 | 37.4 | 4.6 | 19.0 | 2.6 | 1.0 | 9.2 | 24.1 |
| 衛生管理者 | 25.2 | 31.8 | 4.3 | 26.2 | 11.2 | 1.7 | 12.5 | 24.7 |
| ITパスポート | 33.3 | 12.8 | 0.0 | 10.3 | 41.0 | 0.0 | 25.6 | 12.8 |
| MOS | 23.8 | 23.8 | 0.0 | 9.5 | 38.1 | 0.0 | 14.3 | 19.0 |
| 語学検定 | 27.3 | 36.4 | 6.1 | 9.8 | 22.7 | 2.3 | 11.4 | 23.5 |
| 簿記 | 29.4 | 25.9 | 8.0 | 10.9 | 18.4 | 1.5 | 8.0 | 28.9 |
| FP | 23.1 | 19.2 | 0.0 | 15.4 | 34.6 | 3.8 | 11.5 | 23.1 |
| 中小企業診断士 | 40.0 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 45.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
| 社会保険労務士 | 28.6 | 42.9 | 7.1 | 16.7 | 42.9 | 0.0 | 11.9 | 11.9 |
| 社内資格・検定 | 44.0 | 23.3 | 9.5 | 28.4 | 11.2 | 1.7 | 20.7 | 14.7 |
調査の結果、資格取得者に対する人事管理上の措置は、おおむね3つタイプに分けられます。
①昇進・昇格型
②配置・異動型
③一時金支給型
資格取得者に対する人事管理上の措置一つ目は「昇進・昇格型」。業務に関する資格を取得することで、昇進や昇格に影響するタイプです。

昇進・昇格の回答が最も多かった資格は「簿記」と「社内資格・検定」。
とりわけ「社内資格・検定」は、4割以上の企業が昇進・昇格に影響すると回答しています。
資格取得者への措置二つ目のタイプは「配置・異動型」。業務に関連する資格の取得によって、配置転換や人事異動に影響を与えるタイプです。配置転換や異動では、従業員の保有スキルを判断材料にするケースがあります。

配置・異動の回答が最も多かったのは以下の4資格。
〇 安全管理者
〇 衛生管理者
〇 語学検定
〇 社会保険労務士
従業員の保有スキルは管理部門が「人事データ」として管理しています。希望の部署やポジションに異動できる可能性が高くなるので、業務に関する資格を取得したら管理部門へ申告しておきましょう。

資格取得者への措置三つ目のタイプは「一時金支給型」。
資格の取得後、会社へ申請すると「一時金」として給与とは別に支給される場合があります。一時金の回答が最も多かったのは以下の5資格です。
〇 ITパスポート
〇 MOS
〇 FP
〇 中小企業診断士
〇 社会保険労務士
一時金の名称は「合格報奨金」「祝い金」など企業によってまちまち。金額も資格によって異なりますが、難易度の高い資格ほど一時金の額も高くなる傾向にあります。
ほかにも人事管理上の措置として、毎月の給与に手当を上乗せする「手当支給型」、資格取得時に対象者を表彰する「社内表彰型」といったタイプがあります。
上記のとおり、何らかの形で褒美をもらえる企業が多いので、業務関連の資格を取得したら早めに職場へ申告しておくことをおすすめします。
\資格のサブスク!60講座以上ウケホーダイ/
まとめ
以上、企業における資格の評価と取得支援の方法を解説しました。

企業の大半は、業務に関する資格を「何らかの形」で評価しています。
希望の部署やポジションへの異動、昇進昇格など様々なメリットが期待できるので、キャリア形成の一環として、ぜひ資格に挑戦してみましょう。
別記事で、人事労務にオススメの資格16選を紹介しています。気になる方はこちらもどうぞ。