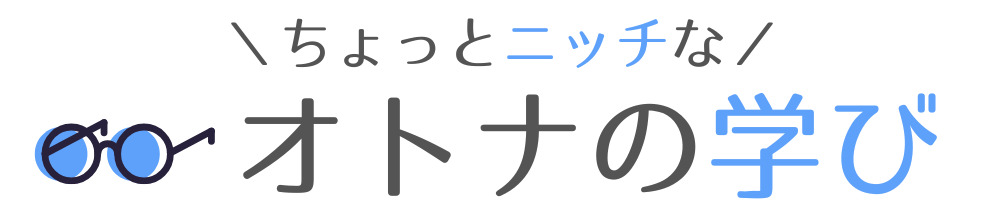MBA取得や学び直しのため大学院進学を検討する社会人の方は、こんな悩みを抱えていませんか?
・社会人に有利な入試制度はどれ?
・大学院入試科目と対策が知りたい
そこで本記事は「社会人におすすめの入試制度」を紹介。

大学院の主な入試制度4つを紹介し、それぞれの違いを比較します。
加えて大学院入試科目の組み合わせパターンと入試科目ごとの対策も解説。大学院入試の具体的なイメージがつかめます。
自身の大学院進学経験をもとに各校の入試情報を分析した内容となっているので、大学院を目指す社会人の方はぜひ参考にしてみてください。
\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/
社会人におすすめの入試制度
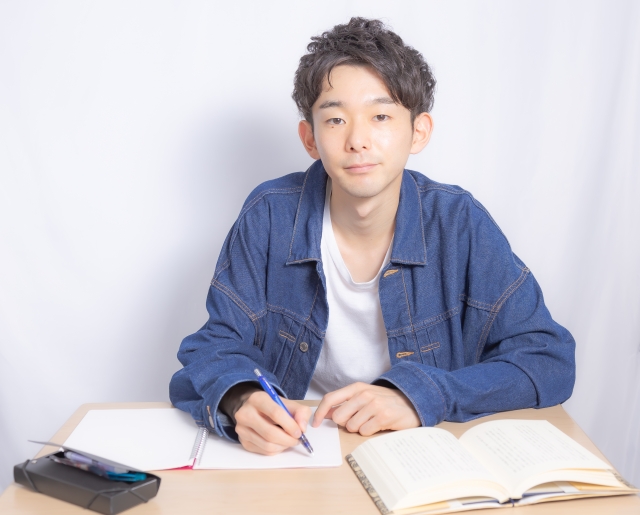
大学院進学を目指すには、まず入試制度の違いをおさえましょう。

制度によって入試対策の仕方が変わるからです。
社会人が受験できる大学院入試制度は以下の4つになります。
【社会人が受験できる入試制度】
・一般入試(専門科目や英語有り)
・社会人入試(面接や小論文が主)
・企業推薦入試(特定の企業のみ対象)
・自己推薦入試(実績ある人のみ対象)
一般入試は、大学卒業後そのまま大学院を目指す学生と一緒に受験する制度。研究系の大学院の場合、専門科目や語学試験を課すことが多いです。試験対策の負担が大きく、現役大学生との勝負になるため、社会人には不利な制度になります。
社会人入試は「実務経験3年以上」など、社会人としての実務経験を出願の条件とする制度です。忙しい社会人に配慮し、試験対策の少ない科目で入試が組まれます。主に「面接」や「小論文」がメインとなるため、働きながらでも受験しやすいメリットがあります。
企業推薦入試は、その大学と協力関係にある企業に勤務する方が受験できる制度になります。社会人入試と同様、試験対策の負担が少ないのが特徴です。社内で希望者を募って企業が学費を負担するケースもあれば、一定の条件に該当する社員が自費で進学する場合もあるなど、支援方法にはバラつきがあります。
自己推薦入試は、志望する研究科や専攻の領域で高い実績や資格を有する人を対象とした制度です。出願条件は大学院ごとに異なります。社会人入試同様、試験対策の負担が少ない分、自己推薦書の出来が合否を左右します。

お勧めは「社会人入試」と「企業推薦入試」です。
社会人入試は、MBAプログラムを設ける大学院のほとんどが採用しており、他の制度より受入定員が多いのが特徴。進学先の選択肢も豊富なので、自分に合う大学院を見つけやすくなります。企業推薦入試は、書類選考なしで面接を受けられる大学院もあるなど、他の受験生より有利な条件で受験できるメリットがあります。
一方の「自己推薦入試」は、大学院によって推薦条件がバラバラ、かつ受入定員も社会人入試より少ないのが難点です。「一般入試」は試験対策に時間がかかる上、現役バリバリの大学生と競うため、社会人には不利な制度。よほどの理由がない限り「社会人入試」または「企業推薦入試」での受験をおすすめします。
大学院入試科目の組み合わせ

社会人が大学院を受験する際の入試科目は、以下の5パターンに分類できます。
【大学院入試科目のパターン】
①書類選考+面接
②書類選考+面接+小論文
③書類選考+面接+専門科目
④書類選考+面接+小論文+専門科目
⑤書類選考+面接+小論文+専科+英語
社会人が大学院を受験する際の一般的なパターンは①と②。

「社会人入試」と「企業推薦入試」でよく見受けられます。
大学院により面接や小論文の形式が異なるので、志望校ごとに傾向を把握した上で試験対策する必要があります。
③④⑤の「専門科目」は、志望分野(MBAなら経営学)における大学卒業レベルの知識を問う試験のこと。

「一般入試」に多いパターンです。
大学院によっては専門科目のなかで英語力を問う場合もあります。また書類審査に小論文を含めたり、面接で口頭試問を行ったりと専門知識の問い方は大学院によってばらつきがあります。
大学院入試科目の特徴と対策

面接
大学院入試の面接は、出願時に提出した「志望理由書」や「研究計画書」をもとに実施します。

志望理由や研究内容に対する考えを整理しておくのがポイント。
身近な人に模擬面接の相手をお願いしてみるのも手です。核心をつく質問をされたり、実際の面接で同じことを聞かれたりと本番に向けた練習になります。
面接の練習相手がいない場合は、予備校の模擬面接講座を利用しましょう。面接で聞かれるポイントや回答例など、プロの目線でアドバイスしてくれます。
別記事で大学院入試の面接対策を詳しく解説しています。気になる方はこちらをご覧ください。
小論文
大学院入試の小論文は、指定されたテーマについて「800~1,000字程度」で自分の主張をまとめる形式が一般的です。

入試の出題パターンは以下のとおり。
・社会問題の事例をもとに意見を論じる
・長めの課題文を要約して意見を論じる
・グラフやデータを分析し意見を論じる
小論文の場合、大学院によって主な出題パターンは決まっています。

志望校が決まったら、過去問を入手し出題傾向をおさえるのがポイント。
字数が少なくても、論文としての構成や作法が求められるので、解答事例を読み込んで論文の構成を把握しておきましょう。
【大学院入試における小論文の構成】
①序論
・問題提起。
└何に関する文章か明らかにする
・設問が特定のテーマに関する場合は
結論を述べる
②本論
・結論を導き出すに至った根拠を論じる
・主張に対して想定される反論に応える
・データや客観的事実に基づいて論じる
③結論
・序論が結論の場合はシンプルに記述
小論文試験は、制限時間内に書くトレーニングも重要です。大学院の過去問を活用して、制限時間内に書き上げる練習が欠かせません。
書き上げた小論文を他人に読んでもらい、論理展開を中心に意見をもらうのも論文の質をあげる一つの手。頼める相手がいない場合は、予備校における小論文講座の活用をおすすめします。
\国内MBA入試の小論文対策ならアガルート/
専門科目
「一般入試」で受験する場合、専門科目として志望研究科の専門分野に関する筆記試験が課されるのが一般的です。

研究系の大学院では、進学後の研究に必要な基礎知識が試されます。
そのため、該当分野の基本的な理論や用語は必ず覚えましょう。完璧を目指すより基礎をおさえて失点を少なくするのが合格のポイントです。
未経験から臨床心理士を目指して指定大学院に進学するケースでは、学問的下地がないところから試験対策します。

その場合、基礎を網羅的に学べる入門書の読み込みから始めるのがベター。
大学院入試では、多くの受験生が読んでいる代表的な専門書が分野ごとにあるので、入試説明会や個別相談会の際に情報収集してみましょう。
また国内MBAや臨床心理士指定大学院など人気のあるコースは、専門の対策講座を設ける予備校もあります。独学での対策に限界を感じる方や一発合格を目指す方は予備校の活用を推奨します。
\業界No.1!令和6年度国内MBA合格者132名/
英語
大学院入試の英語試験は、専門分野に関する英文のリーディング・ライティング問題の出題が多く見受けられます。

そのため専門用語の英単語をマスターしておくことがポイント。
英語力を基礎から高めるのは時間がかかるので、英語が苦手な人ほど早めに対策を始めましょう。
英語試験を課さない代わりにTOEFL®やTOEIC®のスコア提出を求める大学院もあるので、大学院ごとに求められるスコアを確認しておきましょう。
MBA入試対策として、TOEFL®やTOEIC®のスコアアップ講座を開講する予備校もあります。短期間でスコアアップを図りたい方は予備校の活用をおすすめします。
別記事で大学院入試の英語試験を詳しく解説しています。詳細が気になる方はこちらをどうぞ。
まとめ
以上、大学院を目指す社会人におすすめの入試制度と入試科目の組み合わせと科目別の対策を解説しました。

社会人の大学院入試は「社会人入試」か「企業推薦入試」での受験がお勧め
実務経験を活かし有利な条件で受験することで、大学院合格の可能性が高まります。
別記事で、社会人が大学院へ進学した後の苦労や仕事と両立させるための時間の使い方を解説しています。気になる方はこちらもどうぞ。